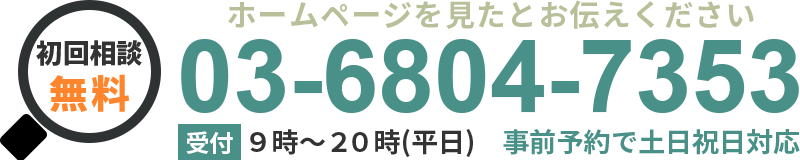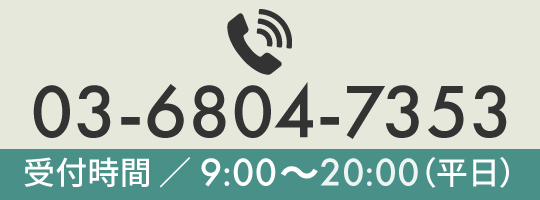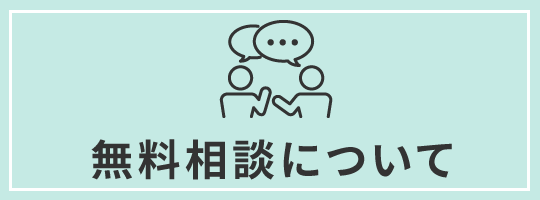Archive for the ‘未分類’ Category
信託、金銭の信託に関する現実的な問題
将来の認知症対策や相続対策などで多くのご家庭で検討されるようになった信託。当社では代表が司法書士であることからその知識と経験を活かし、信託だけでなく遺言・任意後見・死後事務委任契約などからその方の実情にあった認知症対策・相続対策を一緒に考え、提案しています。信託の特徴は「総合力」。認知症対策や相続対策を一括で総合的に進めることができます。このような守備範囲の広さから選ばれることも多い信託ですが、実は意外な課題もあります。それは法律的な問題だけでなく心理的な部分も多い問題。実際に実務を多く経験している司法書士でもある代表者が、現実に起こる信託の問題についてお話します。
信託エピソード「お金をとられる!」
お母さまの認知症対策として、娘さんから遺言と信託の相談を受けた時のことからです。ご家族の考えやご家庭の状況を良く伺い、それを踏まえて遺言・任意後見・死後事務委任契約・信託のメリット・デメリットについて説明しました。ご家族から特に認知症対策が重要な自宅について信託、それ預貯金や有価証券などの財産は信託よりも、遺言で対応することになりました。
信託で浮き彫りになった意外な課題
まずは遺言を作成し、次に信託に取り掛かりました。ここで意外な課題が持ち上がります。それは信託の対象とする現金でした。このご家庭における相続対策では、預貯金が遺言をメインで対応します。しかし、通常は信託で金銭がゼロということもありません。このご家庭の信託ではご自宅が対象財産の中心ですが、不動産の管理のためにも一定の金銭は信託の対象とするべきでした。しかしここで問題が起こりました。金銭を信託の対象とするということは、預貯金をご本人の口座から信託財産管理用の口座に移すということです。このお金を移す作業をすることが信託契約書の作成が進み、私がご家族のみなさんへの説明を進めるに連れ、臨場感をもってお母様が強く認識をされました。そうするといつのまにかお母様の認識が「娘にお金をとられる!」に変わっていきました。思えば遺言の作成をしたときも、少しその兆候はありました。「遺言を作成するとそのに書いたお金については使えなくなるのですか?」と2回ほど質問を受けました。その時は「そんなことはありません。遺言が効果を発揮するのは相続発生後です。もしも相続発生後に書いてある財産が無くなった場合はその部分の効果が無くなるだけで、遺言に書いたからと言ってその財産を使ったり売ったりすることに全く制限はありません」と説明をしてきました。その時にもう少し相続対策によって自分の預貯金が失われるという不安にしっかり対処しておくべきだったと反省もしました。
実際に信託をするということは財産を失うことなのか?
では預貯金を信託したり、不動産を信託することは本当に財産を失うことなのでしょうか。そうではありません。よく信託では「受託者に所有権は移転するが受託者固有の財産になるのではない」と表現されます。聞きなれない言い回しですが後半の「受託者固有の財産になるのではない」という部分に注目して頂きたいと思います。まず受託者というのは財産を管理する人とお考えください。今回紹介したケースでは受託者になるのは娘さんでした。娘さんはお母さんの信託の対象となった財産を管理します。ここでポイントとなるのはその管理方法です。この管理方法が信託の最大の特徴とも言えるかも知れません。財産を管理するということは、財産を預ける方以外の第三者とのやりとりも出てきます。信託財産となった預貯金で必要な支払いを済ませたり、自宅不動産の庭の剪定をしたり、介護施設に入居する時などは売却する権限も持ちます。例えば自宅を売却する場合は、「私が管理しています」といってもその不動産の名義(登記)が本人のままだったらどうでしょうか。相手はあなたが管理者だからといって名義を移す以上、本人に本当に売却する意思があるのか確認しなければなりません。その時、もしもご本人が認知症になっていたら判断能力がなく、意思も確認できないと受け止められ必要な売却が出来なくなってしまいます。そこで信託では「管理のために」「所有権を移転する」のです。受託者に所有権を移転することで売却する時購入者は、受託者から不動産の譲渡を受けることができるようになり、本人に認知症になっていても対応ができるようになるのです。このように所有権を移転することはスムーズな管理や処分のため、必要なことです。しかし所有権を移すと言っても受託者の「固有」の財産となるわけではありません。この言い回しが分かりにくく微妙なのですが要は自分の財産ではないということです。もちろん、自分のために使うことはできません。自分個人の財産とは分けて口座を用意し、決して自分の財産とは混ざらないようにします。そして、その財産を本人のためだけに使います。つまりとられるわけでは全くありません。
司法書士からご本人への説明
上に書いたようなことについて、ゆっくりとご本人に説明をしました。信。託の対象とする金銭が比較的少なかったこともあり、納得をいただけました。そして、この信託の財産管理について説明をしている時、もしかしたらお金をとられるという不安は本質ではないのかなと感じたことがあったのです。
ご本人の本当の想い
ご本人への説明は、娘さんの仕事の都合もあって私1人で行いました。そうすると、少しご本人から雑談めいた話もしてくれました。その中に「娘は相続だとか何か用がある時しか連絡をくれない」といった話やご本人が現役でお仕事をしていた時の話などがありました。そうした話を伺っているうちに、ひょっとしてお金をとられる不信感というより、娘さんとコミュニケーションの糸口を探しているような気がしてきました。遺言、信託と続いたため今回の相続手続きはそれなりに長期に及びました。しかし遺言は順調に終わり、信託もスムーズに進むとそう遠くないうちに終わります。そうすると、おそらくまた娘さんからの連絡の頻度はグンと下がるでしょう。本当にお金をとられると思っているというより、娘さんとのコミュニケーションの材料が無くなってしまうのが寂しいのではないかと感じました。そのため第三者の私が2人で説明するとあっさりとご理解をいただけたような気がします。というより最初から理解はしていたものの娘さんにはどうしても素直になれなかったりなるべく長い間話をしたかっただけのように思います。もしかしたら、娘さんもその事を分かって、仕事もあったのでしょうが説明を私に託したのかも知れません。
普段のコミュニケーションがスムーズな認知症・相続対策につながる
今回のケースでは、もしかしたら普段からのあんまり中身はない電話での雑談などで、もっとスムーズに進められたかも知れません。現役社会人は忙しいし、仕事で頭がいっぱいになりがちです。私も全く人のことはいえないのですが、少し自分が落ち着いた時間で5分、10分の電話をするだけで違うのかも知れません。
信託・遺言などの認知症と相続対策はタケミ・コンサルティングへ!
今日は司法書士として経験した信託のエピソードについてお話ししました。タケミ・コンサルティングは司法書士だけだと相談していいか皆様が迷われることもお手伝いしたいとう考えから設立しました。司法書士や宅地建物取引士としての経験を活かし、俯瞰した目線でみなさまのご相談にのぅていきます。士業としてのネットワークから皆様に必要な対策を各種の専門家と連携して進めていきます。どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】にお任せください
対応エリアも会社のある世田谷区だけでなく北区・葛飾区・江東区などの東京23区や相模原、川崎、横浜、柏、さいたま市などの首都圏でご相談を承っております。どうぞお気軽にご相談ください!
対応エリア | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】にお任せください

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
相続時に「ケリをつけたい」墓じまい
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と、相続や信託や任意後見契約のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!下北沢司法書士事務所として相続登記や遺産承継手続き、成年後見人への就任、遺言の作成などに取り組んでいます!
墓じまいと相続
相続の際に一気に噴出する墓じまい問題。故人の生前はなかなか言い出しにくいまま、相続が発生してしまう。こんなことは良くあります。本音では墓じまいしたいと思っているがなかなか言い出しにくい。相続に関係する兄弟・親類も積極的に触れようとしないが、みんなで協力してお墓を維持しようする雰囲気でもない。こういうお困りごとを相続と一緒に相談されることも多いです。こういう祭祀はまさに心の問題であるため、財産の分配の相続の話とはまた違う切り口で考える必要があるかも知れません。今日はみなさんと一緒に、相続と墓じまいの問題について考えていきたいと思います。
「心の問題」の難しさ
司法書士として相続に携わっていますが、その多くは遺言の作成や遺産分割協議、相続登記など「財産の分配」に関することです。しかし、実際にはそれだけの財産が残ったのは実は相続人の誰か1人の献身的な自宅での介護があったかも知れません。また、民法上は「特別受益」と言いますが相続人の誰か1人だけ、結婚や自宅不動産の購入などの場面で亡くなった親から経済的な支援を受けているかも知れません。このように相続や遺産分割協議では、「確定した財産の分配」をするだけにとどまらず、過去の経緯が反映されることも珍しくありません。過去の経緯が反映されるということがそれだけ感情ものりやすいことになります。司法書士としての当事務所の経験では、やはりこの「感情」の調整がスムーズな相続にする上で大きなテーマになります。法律がどうなってるとか、合理的な損得だけでみんなが判断するなら、こんなに世の中で相続が難しいと思うこともなく、「争族」なんて造語が生まれることもなかったと思います。お墓の問題はある意味究極の「心の問題」と言えると思います。先祖代々の墓をそのまま継承したい人と、今の時代に合わずお墓の維持・管理はもはや困難と考える人がぶつかりやすい場面です。多くの人にとって、難しい問題です。
遺産分割協議前に決めたい
実際に実務で活躍なされている弁護士さんや司法書士が身に染みて感じることですが、現実は理屈通りいかないことが多いです。理屈で考えれば、遺産分割協議にお墓の話を持ち込まず、財産の分配を先に済ましてお墓はのちのちゆっくり解決する課題としても構いません。実際にそういうご家庭はいくらでもあります。しかし、家庭によってはこの考え方が後に大きな問題をもたらすこともあります。遺産分割協議が終わるということは財産の分配の仕方が確定するということです。墓じまいをするかどうかに関わらず、自分の取り分は確定します。更にこの後、銀行で預貯金の払い戻しをしたる不動産の名義変更(相続登記)も済ませれば、完全に相続手続きが終了し相続人1人1人の銀行口座に相続した預貯金が振り込まれることになります。この後に墓じまいをするために費用の出費をお願いしても人によっては出金を損と感じて協力を得られないこともあるかも知れません。その時、その協力しない人は「お金を払うのは嫌だから協力しない」とは言わないでしょう。おそらく「先祖から続くお墓を私たちの代で失くして良いのか」とか「先祖への感謝の気持ちを忘れたのか」とかもっともらしいことを言うと思います。そういわれたらなかなかなにも言い返しようもないとあなたが引き下がり、お墓をそのまま維持する。そうすると結局はお墓の近くに住んでるあなたがずっと掃除をはじめとした維持・管理をすることになり、負担は被る。まだ体が動く今なら良いが老後のことを考えると凄く不安。結局疲れて全額自分で負担して墓じまいをする。そんな状態になってしまうかも知れません。もしもあなたに墓じまいしたいという気持ちがあり、他の相続人の中にお金に細かかったりお墓に思い入れのある方がいる場合は、やはり遺産分割協議と同時にお墓の話も議題として自分から言う方が良いでしょう。自分から言い出すというのは心理的なハードルが高く、またその事で批判めいたことを言われて嫌な思いもするかも知れませんが、もし頑張れそうなら頑張りどころだと思います。
相続税納付のタイミングも見越しながら墓じまいを考える
墓じまいが費用がかかる話であることを考えると、それを相続したお金で済ませないと経済的に大変かもしれません。そして、相続でお金がかかるのは墓じまいだけではありません。相続でかかるお金の代表格が「相続税」です。相続税は被相続人(相続される人)が亡くなってから10か月以内に納付するのがルール。現実的に納付をスムーズに行うには、相続税納付までに実際に相続人の口座に預貯金が振り込まれているのがもちろん望ましいです。実際に司法書士として相続実務に携わっていると分かるのですが、銀行に相続の手続き書面を提出して相続人の口座にお金が振り込まれるまで、思いのほか時間がかかるのです。およそ3週間ほどはかかると思います。墓じまいは期間的な制限はないですが、他の相続のテーマである相続税の納付に引っ張られ、できれば墓じまいも早めに相続人同士の意見をまとめたいという場面も珍しくありません。
もちろん、相続発生前から課題解決できればそれがベスト
これまで墓じまいをいつまでに考えればいいかということについてお話してきました。遺産分割協議や相続税納付を見越してそれより前に決めていくのが良いとお話ししてきましたが、それより早い分には越したことはありません。将来、相続について考える必要のある方の遺言を作成するタイミングであったりそれ以外でもお墓について家族で話し合うタイミングがあれば、早めに決めていくのがベストです。
なにからはじめていいか分からない方は・・・
もし墓じまいをしたいかどうか自分でも結論を出せない、したいけど何からはじめて良いか分からないという方は、まずは現状を把握することからはじめるのはいかがでしょうか。具体的には、墓石に刻まれている方の戒名の数を数えに行ってみましょう。墓じまいするときは今のお墓に眠られている方を永代供養することになるかと思います。永代供養は「一柱いくら」で費用が決められることが多いので、まずは自分の家のお墓に何人眠っているかを把握することは、費用感覚を掴むうえで必ず必要になる作業です。戒名に刻まれておらずお墓に眠っている方もいるかも知れませんが、だいたいは戒名の数イコールお墓に眠っている方の人数と思って良いでしょう。その方たちのお名前を墓石で確認すると「この戒名ははおじいちゃんかな?」「これは誰だろう。遠い昔のご先祖様かな?」とか色んなことを思って感慨深いものもあるかも知れません。
相続・遺産分割協議の相談はタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!!
今日は相続や墓じまいについてお話しました。司法書士として相続や遺産分割協議の実務経験に加え、今日お話しした墓じまいのように俯瞰した視点ももっているのが当社の特徴です。費用的にも司法書士にかかる費用と同水準であり2社分かかるようなこともありません。エリアも事務所がある世田谷区を中心に東京23区はもちろん、調布・府中・町田・吉祥寺などの東京都下や柏・松戸・川崎・横浜・相模原・取手などの首都圏で受任実績があります。事務所から遠方でも札幌、神戸、山形、群馬、千葉の房総地方などの出張実績があり全国に出張対応します。ぜひお気軽にお問合せください!
対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティン

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
実務家がこっそり教える信託・遺言・後見の関係
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と、相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!下北沢司法書士事務所として信託組成や成年後見人の裁判所への手続き、遺言の作成などに取り組んでいます!
信託・遺言・後見。結局どれがいいのか?
今日は司法書士でもある相続コンサル会社として、信託や遺言、後見の関係性についてお話しします。この3つは認知症対策や相続対策として良く紹介されますが、結局どれが一番いいのか分からないという声をよく聞きます。そこで今日は細かいことはバッサリ省きつつ、この3つの関係性についてざっくりとしたイメージをもってもらいたいと思います。今日の話は専門書に載っている説明でもないですし、実際に信託・遺言・法定後見・任意後見を司法書士として経験した実務感覚です。実際に実務をしている法律家だからこそ法律の細かい部分をあえて切り落として説明することができます。
3つの中で一番いいのはズバリ「信託」
信託・遺言・後見(任意後見・法定後見)の3つの中でどれが一番いいのかと聞かれれば、ズバリ信託が一番いいです。なぜなら信託は遺言の効果と後見で得たい効果の大部分を得ることができるからです。信託には必ず「終わりの時期」と「終わった時の信託財産の処分の仕方」を決めます。この「終わった時の財産の処分の仕方」が遺言に該当します。信託では当然、財産の処分の仕方だけを決めるわけではありません。どの財産を信託の対象とし、その財産をどのように運用していくかも決めます。この部分が法定後見・任意後見に該当します。法定後見・任意後見には「身上監護」と「財産管理」の2つの役割がありますが、実際に一般の方がつまづくのが「財産管理」です。具体的には不動産売却などの財産処分などが認知症によりできない、これが財産管理にあたりますがここでつまづくことが多いのです。この財産管理の部分は信託でフォローできるので、信託は「遺言」と「法定後見・任意後見」をおおまかに兼ねることができます。
ただし、信託では「大げさすぎる」ことも多い。
道具というのは、なんでも大きくて強烈な方がいいというわけではありません。ちっちゃぃミニトマトを切るのには大きな中華包丁より小さいナイフの方が向いているでしょう。家庭によっては信託では大げさすぎることも多いです。財産の分配の仕方だけ決めればいいのであれば、信託でなく遺言で十分です。また、認知症になったときの不動産売却だけ念のために対応しておこうというなら任意後見も検討してみるべきです。信託はかなり広範囲をカバーできますが、それだけに専門家費用などが高くなります。信託契約書を家庭の状況に合わせて皆様の打ち合わせしながら1件1件オリジナルで作成、作成した契約書案をベースに公証役場や信託口口座を開設する金融機関と文案調整、更には不動産登記も必要でありそのボリュームも通常の不動産登記より非常に大きいなど、やることの多さと求められる技術の高さから費用も高上りになりがちです。自分の家にとってそこまでやる必要がないのであれば、遺言や任意後見で十分。自分の家庭にはどの程度の対策が合うのか、専門家と相談しながら決めていく必要があります。
信託でも遺言や後見の「全て」をフォローできるわけではない。
ここまで、ざっくりと信託・遺言・後見(法定後見・任意後見)の関係性についてお話してきました。しかし、これは大づかみのイメージであり、実際には信託で「完璧に」遺言や後見でできることをフォローできるわけではありません。少し遺言や後見でできても信託にはできないことも、ご紹介したいと思います。
信託では「全ての財産」の分配を決めることができない。
信託は、「対象となる財産」を決めなければなりません。本人の持っている預貯金、不動産、株などから何をどの程度信託の対象とするのか決めなければならないのです。せっかく信託をするなら不動産は対象とすることが多いですが預貯金には法律とはまた違った難しい問題があります。実際に信託契約の組成を司法書士やコンサル会社の立場で経験しているとよく発生する課題なのですが、預貯金を信託の対象とすることをご本人が嫌がることが多いのです。なにかお金をとられてしまうような感覚になるようです。法律的・合理的に物事を見れば信託の対象とされて預貯金はあくまで本人のために使ったり運用していくものですし、必要なお金は出費してもらうことができます。ですが一方で預貯金が入金されている口座の名義が変わるのも事実。これをお金をとられてしまうような感覚になって不安になり、預貯金を信託の対象とするのを嫌がる方は非常に多いです。この場合、信託で預貯金を全く対象としないのも稀なケースですから、本人が納得できる程度の金額を信託の対象として対応することになります。例えば数十万円とか50万円ほどだと納得してもらえることが多いです。このように、預貯金の大部分が信託の対象とできないことも良くあります。そうすると、信託の対象とならなかった預貯金については遺言を作らないと財産の分配について定まらないことになります。信託と同時に遺言も作成する必要が出るかも知れません。また、本人に預貯金を信託の対象とすることがスムーズに納得してもらえたとしても、全ての預貯金を信託の対象とすることは現実的ではありません。これから支給される年金は信託の対象と現実問題としてできませんし、預貯金の全てを信託対象としてしまうと本人のちょっとしたお小遣いも手元にはなくなり管理者に要請して出勤してもらうことになるのでさすがに不便です。預貯金の大部分を信託の対象と出来ればごく簡単で良いでしょうが、遺言は合った方が相続時の手続きに便利です。
介護施設の契約権限は「任意後見」「法定後見」でないと得られない。
信託の対象となるのはあくまで「財産」です。人が世間とやりとりする上で「財産」・・つまりお金まわりの話以外にもう1つ大きなテーマがあります。それは「身分上の行為」。自分の身の回りの話で例えば介護施設の契約などはこれに当たります。介護施設の契約をすることは実際にその施設で生活することを意味しており、実際の生活が大きく変わることになります。こういう自分の生活が変わるような話は財産の話とはまた別であり、財産しか対象とできない信託では対応できません。この身分上の行為に対応できるのは「任意後見」や「法定後見」です。なので、この部分を対応したければ信託とは別に任意後見契約を締結する必要があります。・・ただ、現実問題としては介護施設の入居などは家族が代行すれば入居に応じる施設が多いように思います。いちいち「ご本人が認知症なので後見制度を利用してください」とお客さんに言ってしまっては、話が進まないと思います。ただし、これは「実際には問題にならないだろうな。何とかなるだろ」というだけの話で法律的に、確実に介護施設に入居できることを固めたいなら信託と同時に任意後見契約を締結すると良いです。
信託、任意後見、遺言の相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応します。
今日は信託・遺言・後見の関係性についてお話ししました。様々な法的手段がある中、自分の家にもっともあった方法を選びたい方はぜひタケミ・コンサルティングへご相談ください!下北沢司法書士事務所として基礎から固めたしっかりした法律知識があり、コンサル会社も同時に運営することで俯瞰した広い視点から皆様にあった方法を一緒に考えます。費用的にも司法書士にかかる費用と同水準であり2社分かかるようなこともありません。エリアも事務所がある世田谷区を中心に東京23区はもちろん、調布・府中・町田・吉祥寺などの東京都下や柏・松戸・川崎・横浜・相模原・取手などの首都圏で受任実績があります。事務所から遠方でも札幌、神戸、山形、群馬、千葉の房総地方などの出張実績があり全国に出張対応します。ぜひお気軽にお問合せください!
対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティン

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
弱点解消!?成年後見制度の法改正
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!下北沢司法書士事務所として成年後見制度利用の申し立てや、成年後見人への就任も行っております。
成年後見制度の法改正について動画で解説しました。
少し前に、成年後見制度の法改正案が公表されました。まだ案で発表されたものもAパターン、Bパターンの2種類あり、実際に法改正がされるのは数年かかると思います。しかしこの改正案では、現行の成年後見制度を大きく変えるポイントがあります。その点について動画で解説しました。
成年後見制度の弱点は3つ!改正で解消できるか!?
現行の成年後見制度には大きく3つ、問題があります。動画ではこの3つの問題が解消できるかについて触れました。その問題とは・・・
1 他人が家庭の首を突っ込んでくる問題
成年後見制度を使うと、成年後見人・監督人・あるいが裁判所が関与してきます。自分の家族のお金の管理に第三者が関与することになるので、利用者にとって理不尽に感じる人も多いと思います。
2 横領リスク
本当にごくまれにではありますが、成年後見人による横領事件も発生することがあります。横領は、成年後見人そのものが「やるぞ!」と思ってしまえば防ぐことは無理です(ただ、捕まるので普通はやるぞと思いません)。この横領リスクから来る利用者の不安も、成年後見制度の課題です。
3 一度使うと一生やめられない
成年後見制度を使い始めた理由が解消しない限り、制度利用がやめられません。認知症や重度知的障害が成年後見制度利用の理由としてほとんどなので、事実上一生やめれません。
成年後見制度利用のご相談も司法書士経営の当社へ!エリアも幅広く対応します!!
成年後見制度は使わずにすむなら使わない方がいいです。ただやむなく利用する場合は、できるだけみなさんに考えに沿ったものになるよう、司法書士でもある当社なら先を見据えて提案していくことができます。ぜひご相談ください!エリアも世田谷区、杉並区、中野区など23区の他、町田市や狛江市などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティン

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
動画で解説!死後事務委任契約
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!下北沢司法書士事務所として会社設立業務も行っております!
死後事務委任契約について動画で解説!
死後事務委任契約がどういったものなのか、動画で解説しました!こちら↓↓
頭がちょっとズラっぽぃ気もしますが、気にせずいきましょう!髪のセットもオシャレも自信満々なかっこぃぃ話し方もできませんがいいじゃないか!頑張ってるんだから!!
時代が必要とする死後事務委任契約
死後事務委任契約とはなにか。それは亡くなった後の葬儀の手配や行政手続きなどを契約によって司法書士などに任せる方法です。1人ぐらしであっても、息子夫婦や娘夫婦が近くに住んでいて関係性も良好なのが当たり前の世の中であれば死後事務委任契約がクローズアップされることもなかったと思います。ところが子どもがいなかったり、遠くに住んでいたり、仲が悪く親のことに関わりたくない人が増えてきたりと昔はなかった事情が世間一般にたくさん出るようになりました。終活を考える上で、死後事務委任契約も必要とする人が増えてきました。
死後事務委任契約のご相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!!
今日は死後事務委任契約について解説しました。当社は法律手続きに精通した司法書士が運営しております。ぜひお気軽にご相談ください!エリアも世田谷区、杉並区、中野区など23区の他、町田市や調布市などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
動画で解説!株式会社と合同会社の違い
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!下北沢司法書士事務所として会社設立業務も行っております!
株式会社と合同会社、本当はどう違うのか!動画で解説します。
司法書士として株式会社や合同会社の設立、合同会社から株式会社の組織変更のご依頼をいただくことも多いです。その時に必ずテーマになるのは、「株式会社と合同会社どう違うのか?」。このテーマ、実は深いテーマです。というのは会社法の世界で違いと言われることと、実際に会社運営する経営者に与える影響で若干のズレがあるからです。今日はそのズレについて動画で解説しました。
会社設立はただ単に手続きをとればいいわけではありません。今後どんな形で会社を運営していきたいか、どのくらいの規模の会社を目指すのか、そして何の目的で会社を設立するのかで会社の運営ルール(定款)の中身も変わってきます。将来を見据えた会社設立を目指すなら、やはり専門家に相談しながら進めるのが一番です。
文章の方が見やすい方はブログもあります!よろしければこちらもご覧くださいませ!
起業や会社設立の相談は司法書士経営のタケミ・コンサルティングへ!!
今日は株式会社と合同会社の違いについて動画で解説しました。当社では起業のご相談も承っております。エリアも世田谷区、渋谷区、新宿区など23区の他、府中市や調布市などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士が説明しない!株式会社と合同会社の決定的な違い
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。
司法書士が気が付かない!株式会社と合同会社の本当の違い。
株式会社と合同会社の性質の違い。会社を設立する時も、この違いの説明は多くの場合に司法書士から説明を受けると思います。司法書士にもお勉強タイプの司法書士と経営コンサルタイプの司法書士がいます。このタイプの違いによって説明の仕方や切り口が大きく変わります。私自身も司法書士であり、会社設立登記も平均月1件ほどは申請しています。今日は会社設立の際に本当に気にすべきポイントはなんなのかご説明します。
お勉強タイプは「定款自治の原則」を中心に考える。
株式会社と合同会社の法的な一番大きな違いは「定款自治」の許容度です。株式会社・合同会社ともに「定款」という会社運営の基本ルールを定めることが会社法上、義務付けられています。この定款の自由度の高さが合同会社の方が高い。色んなことを社内ルールで決められます。株式会社はこの自由度が低く、会社法による会社内運営の制限が厳しい。これが法的な一番の違いでお勉強を中心に考える司法書士はこの点を強調します。自由度が高いのですから合同会社のが良いと思うかも知れません。しかし自由にも意外なデメリットがあります。自由に決めた手続きが本当にきちんとして手続きに基づいて決められたのか、争いになりやすいです。この点、株式会社の方がルールが厳格に定まっていて比較の上ではリスクは低いですし何よりも社内運営について議論になる余地が少ないです。会社は常にお客様目線でなければいけません。定款を含めた社内ルールも大事ですが、本当に力を入れるべきはお客様が喜ぶ商品・サービスを提供することです。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社には普通の司法書士があまり説明しないが、実は大きなデメリットとなるかも知れないポイントが2つあります。1つめは会社のオーナーと経営者が同じ人でなければならないこと。株式会社であれば会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)は違う人であることを前提とされており、これを「所有と経営の分離」と言います。なので会社のオーナーでない人が取締役になることはできます。一方、合同会社は「所有と経営が一致」しています。経営者(業務執行社員)になるためには前提として社員(会社のオーナー)でなければいけないため、「会社のオーナーではないが経営は任せる」という選択ができません。そして、会社のオーナーが複数人いた時、そのオーナー同士の力関係はどう決まるのでしょうか。株式会社ならざっくり言えば「出したお金の金額」によって決まります。出資金額に応じてもらえる株の数が変わり、株の数で株主総会での議決権の大きさがあります。一方、合同会社は出したお金の額ではなく「1人1票」が原則です。100万円だした人と1万円出した人が同じ発言力というのは、やはり100万出した人にとっては不合理に感じます。定款によってこの原則を変えることもできますが、適正な社内手続きを取りまたその証拠残しをしないと、紛争リスクがあることは前の項目でお話しさせていただきました。
合同会社のメリットは?
では合同会社にメリットはないのでしょうか。もちろんあります!それが設立費用が安いこと。会社設立時に法務局に収める登録免許税が株式会社なら15万円ですが合同会社が6万円ですみます。それに1人で会社経営していく場合は合同会社のデメリットは問題になりません。1人で経営するなら合同会社で十分ですし、いざとなったら合同会社を株式会社に組織変更することもできます。
起業や事業承継の相談は司法書士経営の当社へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は合同会社と株式会社の違いについて説明しました。起業や事業承継のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!会社設立登記の相談も一緒にすることができます!エリアも世田谷区、渋谷区、新宿区など23区の他、府中市や調布市などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】にお任せください

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
夏季休暇について
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。
夏季休暇は特にとらず、暦通りいきます!
暑い!ちょっと外だけでシャツがビシャビシャになるんで事務所に着替えを用意してます。最近は男性でも日傘が普通になってきたし、異常な暑さの対応にみなさん苦労してると思います。さてその暑いさなか。お盆休みの時期になってきました。帰省や旅行など、予定のある方は熱中症など気をつけていただきたいなと思います。真夏の混雑した東京駅なんて地獄ですからね。出かける前に覚悟と準備が必要です。さて、タケミコンサルティングは特に夏休みは設けず、暦通り営業します。本当は少し休もうかなと思ったのですが兼業している司法書士の方で登記の申請があったり、成年後見業務で対応があったりするので普通に働くことにしました。会社の方も営業しますので、お問合せなどございましたら電話やお問合せフォームでお気軽にお問合せください。お盆休みも意外と帰省、家族サービス、お墓参りなど体力使うものです。もしかしたら、仕事より疲れるかも。みなさん、体調に気を付けてお過ごしください!
タケミ・コンサルティング 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
死後事務委任契約と認知症
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。
死後事務委任契約は認知症でもできるのか。
亡くなった後の葬儀の手配など様々な手続きを委任する死後事務委任契約。独身の方や近しい親族が遠方にお住いの方に良く利用されます。ところで死後事務委任契約を含む終活がらみの制度は認知症とのからみが良く問題になります。死後事務委任契約だけでなく、遺言、信託、成年後見、任意後見、終活とは少し違いますが不動産売却。今日は死後事務委任契約と認知症の関係について解説します。
認知症では死後事務委任契約はできない。しかし・・・
認知症の場合は死後事務委任契約はできない!これが結論ではあります。認知症ということは、自分にとって得か損か全然判断できないし意思を表示することができません。しかし、認知症といっても程度は様々。自分にとって得か損かなんて若くたってなかなか正確に判断できません。ではどの程度物事が判断できれば良いのでしょうか。
意外と多くの方が利用できる
基本的には、認知症かどうかはお医者さんに細かく診断してもらう必要はありません。自分の住所、名前、生年月日が正確にいえて死後事務委任契約を締結意思がしっかり表示できれば大丈夫です。死後事務委任契約は、当社では公正証書で契約締結することをおすすめしております。公正証書を作成する公証人の先生が契約内容について説明しますから、それを理解して公証人に契約締結する意思をはっきり伝えられれば大丈夫出です。
死後事務委任契約のご相談は司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!エリアも幅広く対応!
今日は死後事務委任契約についてお話しました。ご相談はぜひ司法書士運営のタケミ・コンサルティングへ!契約書作成だけでなく司法書士として死後事務委任契約の受任者にもなれ、遺言や信託の相談も合わせてすることができます。エリアも世田谷区、杉並区、中野区など23区の他、三鷹市や吉祥寺などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】にお任せください

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
経営権を保有しながら事業承継を進めるには?
こんにちは!株式会社タケミ・コンサルティングの竹内です。司法書士と相続や事業承継のサポートをするタケミ・コンサルティングの代表を兼業!死後事務委任契約などの終活、相続や信託や遺言などの生前対策、事業承継のサポートをしております。
会社経営の大間違いを防ぐ「黄金株」
会社も長く続いていると相続対策などで株主が分散することが多いです。創業社長の子や孫などに株を少しずつ持たせているうちに、いつのまにか創業社長に会社の重要事項の決定権が無くなっていることがあります。どういうことなのでしょうか。
会社の重要事項は「株主総会」で決まる
会社運営をルールを定めている法律が「会社法」です。会社法では一定の事項を会社の「株主総会」で決めるよう定められています。代表的なものが役員の人事権。経営者である会社の取締役、監査をする監査役などは株主総会に出席した株主の過半数以上の決定によってなされます。人事権は経営権。つまり、持っている会社の株を51%を下回ると会社の経営権を掌握できてない状態になってしまいます。このほか、他の株主が勝手に第三者に株を売却してしまうリスク、持っている株が全体の3分の1を下回ると他の株主の合意で会社を清算されてしまうかも知れないリスクが出てきます。
どう対応する?
このように相続対策をしているうちにいつのまにか経営基盤が弱くなってしまうことがあり得ます。また、経営基盤を保持しながら相続対策のための株式贈与を進めることも事業承継のテーマの1つになってきます。どうするか。1つは民事信託を活用して、株から発生する議決権は現経営者が掌握しながら生前贈与を進めていく手法があります。そしてもう1つ。株そのものの力で会社の経営権を保持していくことが考えられます。それが「黄金株」です。
黄金株とは?
黄金株の正式名称は「拒否権条項付き株式」といいます。あらかじめ「ある一定」の事項に対して議決するにはこの拒否権条項付き株式を保有している株主だけによる「種類株主総会」での議決が必要です。これを創業社長が1株だけ保有していれば、例え99%以上の株を他の株主が持っていても株主総会の議決を「拒否」することができます。例えば人事権につき拒否権条項付株式を設定していれば、他の株主全員が賛成しても黄金株1株を持つ株主が否定すれば承認されません。この黄金株を株式譲渡や会社の解散、あるいは「株主総会議決事項の全て」など、会社の経営を左右する大きなテーマに設定しておけば保有している株主割合が低下しても影響力を保持することができます。
どうやって黄金株を持つのか?
黄金株を持つにはまず定款を変更して「種類株式発行会社」にならなければなりません。会社法108条には普通株式とは効果の違う株式を9種類定められており、黄金株もその中の1つ。株主総会で議決権の3分の2以上の賛成で定款を変更し、種類株式を設定。ここで設定した黄金株を1株だけ発行し創業社長が持ちます。黄金株を設定することそのものに議決権の3分の2以上の賛成が必要なので、やはり生前贈与をはじめる前の創業社長が100%株主の状態で、黄金株を設定しておき、それから少しずつ株式譲渡していくのが理想です。
黄金株のご相談はタケミ・コンサルティングへ!!エリアも幅広く対応!
今日は黄金株についてお話ししました。タケミ・コンサルティングの代表は司法書士も兼業しているため、黄金株のスキーム設計だけでなく株主総会議事録や定款の作成、更には登記申請までご相談いただけます。エリアも世田谷区、新宿区、渋谷区など23区の他、三鷹市や吉祥寺などの東京都下や横浜市、川崎市、柏市など首都圏のご相談に対応。ほか全国から相談を承ることもございます。対応エリアはこちら↓
今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
お問い合わせ | 相続・生前対策や事業承継、M&Aのご相談なら【株式会社タケミ・コンサルティング】にお任せください

東京都世田谷区北沢にある株式会社タケミ・コンサルティングは、相続や事業承継、M&Aのコンサルティングを行っています。代表の竹内友章は、司法書士事務所「下北沢司法書士事務所」の代表も務めており、相続や生前対策、事業承継のサポートを提供しています。また、上級心理カウンセラーの資格も持ち、相談者様の心情に寄り添った対応を心掛けています。終活・生前対策、相続や事業承継に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。